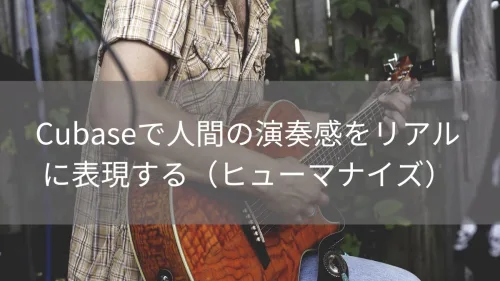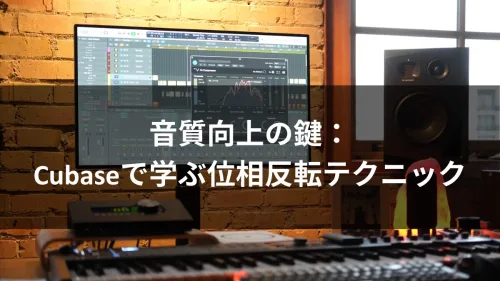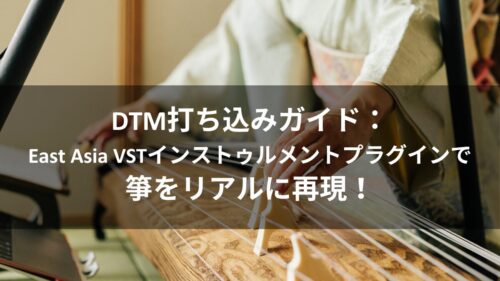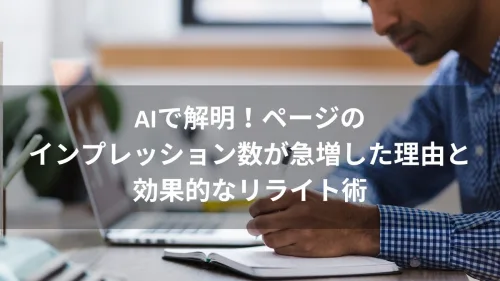タグ
昔の音を再現したいDTMer必見!1960〜2020年代のミキシング・マスタリング技術と名機まとめ
広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

音楽制作では、時代ごとにEQ(イコライザー)・コンプレッサー・リバーブという基本処理の使い方が変化してきました。本記事では、各年代の代表的音源と技術的特徴、さらに代表機材も含めて整理します。
年代別:代表音源とミキシング・マスタリング特徴

スクロールできます
| 時代 | 代表音源 | 特徴と技術傾向 |
|---|---|---|
| 1960年代 | The Beatles「Abbey Road」、 Beach Boys「Pet Sounds」 | テープ録音中心。中域重視で温かみのある音。 リバーブ(プレート・エコーチャンバー)多用、定位も比較的シンプル。 |
| 1970年代 | Pink Floyd「The Dark Side of the Moon」、 Fleetwood Mac「Rumours」 | アナログ卓(Neve/APIなど)で音作り。 空間感と深みを重視。ミックスの“奥行き”を意識。 |
| 1980年代 | Michael Jackson「Thriller」、 Prince「Purple Rain」 | デジタル機器導入。 ゲートリバーブドラムが象徴的。 高域の鮮明さやステレオ感を強調。 |
| 1990年代 | Nirvana「Nevermind」、 Mariah Carey「Daydream」 | クリアでパンチのある音。 リバーブは控えめ。 音の分離と明瞭感を重視。 |
| 2000年代 | Daft Punk「Discovery」、 Linkin Park「Hybrid Theory」 | DAW+プラグイン主体の制作。 マルチバンドEQ/コンプで音圧と透明感を両立。 |
| 2010〜2020年代 | Adele「21」、 Billie Eilish「When We All Fall Asleep…」、 Taylor Swift「Midnights」など | 音圧競争の極点化。 AI補正・自動化も導入。 リバーブは控えめで “近さ” を意識する傾向。 |
代表機材と処理傾向:EQ/コンプ/リバーブ

スクロールできます
| 区分 | 代表機材 | その役割・特色 |
|---|---|---|
| EQ | Pultec EQP-1A、 Neve 1073、 API 550A、 SSL “Black Knob” EQ、 FabFilter Pro-Q など | 初期は真空管・パッシブ型で“音色付け”が重要。 後年はパラメトリック化、モデリング、動的EQ導入。 (参照:The History of EQ in the Studio) |
| コンプレッサー/ ダイナミクス処理 | Fairchild 670、 Teletronix LA-2A、 Urei 1176、 dbx 160、 SSLバスコンプ、 マスタリング用リミッター | 60〜70年代は温かく滑らかな圧縮。 80年代以降はパンチやまとまりを意識。 ラウドネス戦争期には強い圧縮・リミッティング。 (参照:The History of Compressors) |
| リバーブ/ 残響 | EMT 140 プレート、 スプリングリバーブ、 AMS RMX16、 Lexicon 224/480L、 Altiverb、Valhalla 系プラグイン | 初期は物理プレート・エコーチャンバー。 80年代以降デジタル・アルゴリズミックリバーブ全盛。 2000年代以降、コンボリューションや 質感重視のリバーブも普及。 |
補足事例:
- SSL 4000 シリーズの “Listen Mic” 回路に起因するゲートリバーブの誤作用が、Phil Collins の “In the Air Tonight” ドラムに応用されたという逸話もあります。
- “Wall of Sound” 制作手法では重層オーバーダビングとともにエコーチャンバーを活用し、密度あるサウンドを作り出したという説明もあります。
1960〜2020年代のミキシング/マスタリング主要機材リスト

EQ・コンプレッサー・リバーブを中心に、代表的モデルとその特徴を表にまとめました。
(※プロフェッショナル現場での象徴的機材を抜粋)
1960年代:アナログ黎明期(温かみと丸み)
スクロールできます
| 区分 | 代表機材 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| EQ | Pultec EQP-1A | 真空管EQ。高域のシルキーなブースト。低域の厚み。 |
サウンドハウス
PluginBoutique |
| コンプレッサー | Fairchild 670 | 滑らかで温かい真空管圧縮。ボーカルに最適。 |
サウンドハウス
PluginBoutique |
Teletronix LA-2A |
サウンドハウス
PluginBoutique | ||
| リバーブ | EMT 140 Plate Reverb | プレート方式。艶のある残響。60年代ポップの象徴。 |
1970年代:ロック黄金期・テープサウンド
スクロールできます
| 区分 | 代表機材 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| EQ | Neve 1073 | 太く音楽的。ロック定番のアナログコンソールEQ。 | |
API 550A |
サウンドハウス
PluginBoutique | ||
| コンプレッサー | Urei 1176 | 速いアタックでパンチを出す。ドラムやベースに。 | |
| dbx 160 | |||
| リバーブ | AKG BX20 | 深みのあるプレート+スプリング残響。 | |
| EMT 250(初期デジタル) |
1980年代:デジタル革命とリバーブ全盛
スクロールできます
| 区分 | 代表機材 | 特徴 |
|---|---|---|
| EQ | SSL 4000E Channel EQ, Sony Oxford EQ | シャープで明るいトーン。明瞭感を強調。 |
| コンプレッサー | SSL Bus Compressor, Drawmer 1960 | ステレオバス圧縮で“まとまり感”。 |
| リバーブ | Lexicon 224 / 480L, AMS RMX16 | デジタル特有の透明で広大な空間。ゲートリバーブの象徴。 |
Lexicon 224なら下記バンドル製品がお得です。
1990年代:クリアで精密、CDサウンド
スクロールできます
| 区分 | 代表機材 | 特徴 |
|---|---|---|
| EQ | GML 8200, Avalon 2055 | クリーンで正確なEQ。高域の伸びを重視。 |
| コンプレッサー | Manley Vari-Mu, Waves L1 Limiter | 音圧を上げつつ自然な質感を保持。 |
| リバーブ | TC Electronic M3000, Lexicon PCM91 | デジタルながらナチュラルな残響。過剰な深さを排除。 |
2000年代:DAW主流とプラグイン時代
スクロールできます
| 区分 | 代表機材/プラグイン | 特徴 |
|---|---|---|
| EQ | FabFilter Pro-Q, Waves SSL G-EQ | 周波数解析しながら精密補正。アナログ風も可能。 |
| コンプレッサー | Waves CLA-76, UAD LA-2A / 1176 | 名機を再現したデジタルモデリング。 |
| リバーブ | Altiverb, Valhalla Room | 実空間を再現するコンボリューションリバーブ登場。 |
2010〜2020年代:AI・ハイブリッド・ストリーミング時代
スクロールできます
| 区分 | 代表機材/プラグイン | 特徴 |
|---|---|---|
| EQ | Ozone EQ, Neutron 4, Soothe2 | AI補正・動的EQ。耳障り帯域を自動除去。 |
| コンプレッサー | FabFilter Pro-C2, TDR Kotelnikov, Smart:Comp 2 | 透明感・知的圧縮。音圧と自然さを両立。 |
| リバーブ | Valhalla VintageVerb, LiquidSonics Seventh Heaven | アナログ感+立体音響対応。Lo-Fi表現も併用。 |
各年代における EQ カーブ傾向(周波数帯域別)
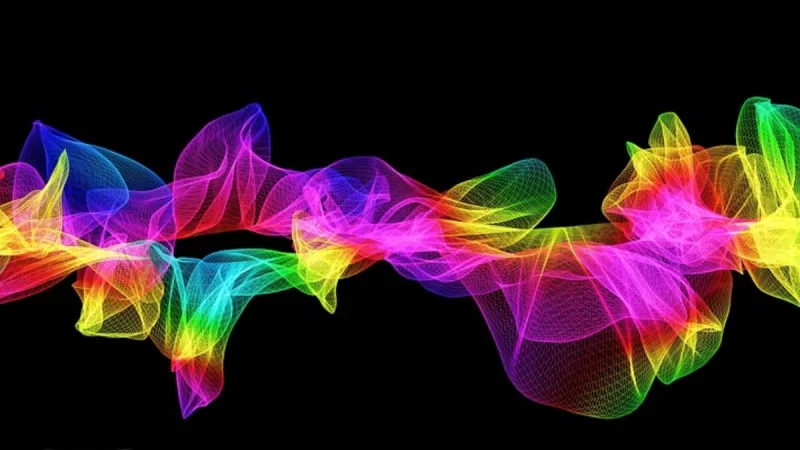
スクロールできます
| 時代 | 低域 (〜200Hz) | 中域 (200Hz〜3kHz) | 高域 (3kHz〜) | 総合傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 1960〜70年代 | やや強調、丸み重視 | 主役帯域として温かみを重視 | 控えめにロールオフ | 中域中心で温かく、定位や厚みを重視 |
| 1980年代 | キック/ベースのアタック重視 | 中域はやや整理ぎみ | 高域を明るく “抜け” を強調 | 華やかで広がりを重視したトーン |
| 1990年代 | 低域をタイト化 | クリア化、不要帯域カット | 空気感を重視して高域を伸ばす | 分離感・明瞭感重視の調整 |
| 2000年代以降 | 50〜120Hzあたりを補強/制御 | 中域を整理しつつ密度を維持 | 10kHz 以上を適度に強調 | 音圧と透明感を両立するバランス設計 |
| 2010〜2020年代 | サブベースからローを慎重に扱う | AI補正や動的EQで帯域移動もあり | 空気感・ナチュラルさを重視した高域 | 自然さと立体感を兼ね備えた “最適化音質” |
PR
今なら、Universal Audio LUNA Pro 2.0のスタート特価で“約45万円分のUADプラグインバンドル”が手に入る
- 21,200円(イントロセール価格)で、プロアナログサウンド+即戦力UADプラグインが一括導入できるバンドルは他に例がありません。
- バンドルプラグイン総額は約45万円分。まさに「プラグイン目当てで買っても損なし」の超お得パッケージです。
- 本場プロ愛用の30種以上がLUNA以外のDAWでもVST/AU/AAX形式で使えます。
- 専用のUADハードウェア(DSPカードやAudio Interface)不要、パソコンがあればOK。初心者でも扱いやすいシンプル設計+AI支援。
クリックして読める「目次」
出典
- 「How the 1990s Changed Recording and Music Production」 (Reverb) (reverb.com)
- 「Mastering Music: A Century Of History」 (Sonarworks)
- 「The Evolution of Music Production Technology: From Analog to Digital and Beyond」 (Illustrate Magazine)
- 「Adoption of AI Technology in the Music Mixing Workflow: An Investigation」(Cornel University)(arXiv)
- 「Solid State Logic SL 4000」(Wikipedia)
- 「Wall of Sound」(Wikipedia)
- 「The History Of Compressors In The Studio」(Vintage King)
- 「The History of EQ in the Studio」(Vintage King)
まとめと今後の展望

- 各年代を通じて、処理方法や機材が進化してきましたが、「音楽的判断」「リファレンストラックとの比較」は常に重要です。
- 最近では AI/自動化/プラグイン技術 がミキシング・マスタリング領域にも浸透し始めています。たとえば AI 補正ツールや自動マスタリングなども議論されています。
- 一方で、古典機材の“個性”を模擬するアナログモデリングやハイブリッド制作スタイルも根強く残っています。
次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!
あわせて読みたい
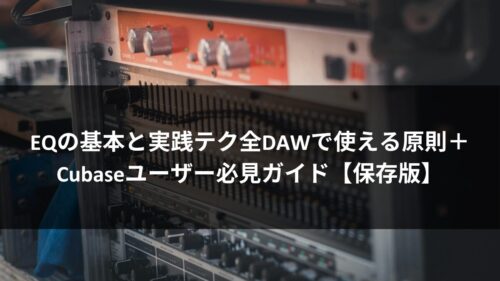
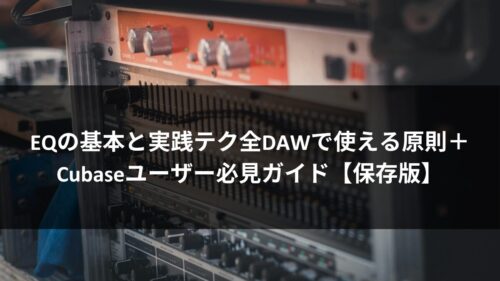
EQの基本と実践テク|全DAWで使える原則+Cubaseユーザー必見ガイド【保存版】
EQの基本と実践テクを徹底解説。全DAWで使える原則からCubaseユーザー向けの応用法まで網羅。スイープ法・プリセット活用・帯域別の調整ポイントを初心者にもわかりやすく解説した保存版ガイド。
あわせて読みたい
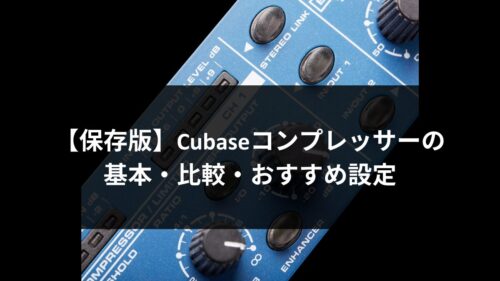
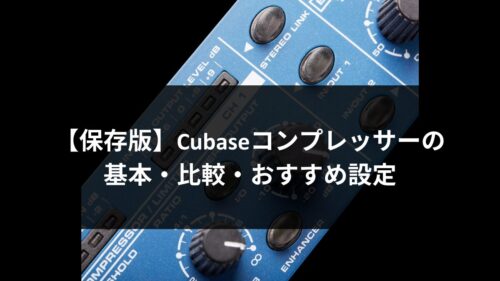
【保存版】Cubaseコンプレッサーの基本・比較・おすすめ設定
Cubaseのコンプレッサーを基本から比較まで網羅。Cubase付属コンプの特徴と設定目安を具体的数値で解説し、自然さを保つパラレルも紹介します。
あわせて読みたい
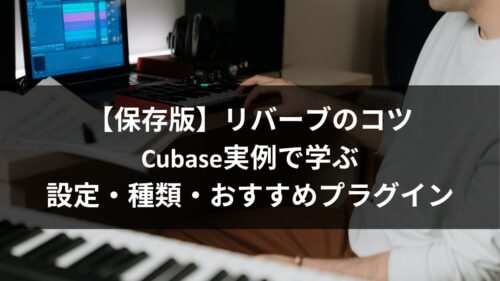
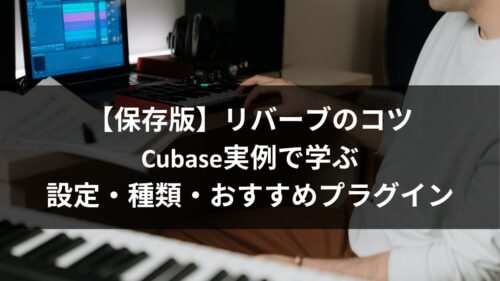
【保存版】リバーブのコツ|Cubase実例で学ぶ設定・種類・おすすめプラグイン
リバーブの設定や種類の違いをわかりやすく解説。Cubase実例を中心にしつつ、他のDAWユーザーにも役立つ内容です。プリ/ポストフェーダーの使い分けやEQ処理、プロ定番のおすすめプラグインまで網羅した実践ガイド。
マスタリング関連記事
最後まで読んでいただきありがとうございました。
独学できる人とは
DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。
スクロールできます
| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |
|---|---|
| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |
独学はちょっと難しいかも…
チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。
DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。
もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。